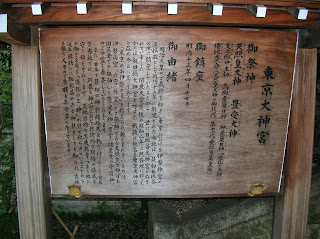EC-CUBE、日本発のOpen Sourceだそうです。
今回は、このEC-CUBEの使い勝手を見極めるべく、自宅のローカル環境に導入することに
しました。
この記事は、ローカル環境のXAMPPにEC-CUBEを導入する手順をまとめました。
結論からいうと、XAMPPが導入されていさえいれば、「CMSの追加作業は簡単」という
感想を得ました。
1、XAMPPにEC-CUBE用のデータベースを作成する。
※XAMPPは設定済みとしてお話を進めさせていただきます。
「http://localhost/」にアクセスし、「ツール」→「phpMyAdmin」をクリックします。
XAMPP導入時に設定したphpMyAdminのユーザ名、パスワードを入力し、実行をクリックします。
phpMyAdminにログインしたら、「データベース」タブをクリックし、「新規データベースを作成する」の
したのダイアログにEC-CUBE用のデータベース名を指定して「作成」をクリックしてください。
tsteccubというデータベース名のDBが作成できました。
以上でphpMyAdminの設定は終わりです。
2、EC-CUBEをインストールする。
入手します。
が、EC-CUBEメンバー(登録無料)となってから出ないとダウンロードできませんでした。
EC-CUBEメンバー(登録無料)の手続きの詳細は省略しますが、表示された画面の指示に
したがって進めれば、なんなく登録は終了するはずです。
登録が完了すると以下の画面が表示されます。
「EC-CUBEメンバートップページへ」のバナーをクリックして、メンバーページへ入り、「無料ダウンロード」のバナーをクリックし「EC-CUBE本体」を任意の場所へダウンロードしてください。
2013年10月17日現在、ダウンロードされたファイル名は「eccube-2.13.0」でファイル形式は
zip形式で落ちてきます。
このファイルを解凍しその中身をデスクトップ等の適当な場所にコピーして中身を出します。
そして、中身のフォルダ名をXAMPPで使用する際にわかりやすい名前にリネームします。
(例)
私の場合、「eccube-2.13.0」を「eccube」にしました。
このリネームした「eccube」フォルダを「C:\xampp\htdocs」(XAMPPフォルダの位置)にコピーします。
ここまでで、ローカル環境にEC-CUBEがインストールされたことになります。
次にEC-CUBEをセットアップします。
ブラウザから。
「http://localhost/eccube/html/install」
と入力しEC-CUBEのセットアップ画面を開きます。
これが出たら、「次に進む」をクリックします。
「チェック結果」画面で、「アクセス権限は正常です」を確認して「次へ進む」をクリックします。
必要なファイルコピーがされます。「コピー成功」を確認し「次に進む」をクリックします。
次に、「ECサイトの設定」[管理機能の設定」「WEBサーバの設定」画面が出てきます。
ここでは「ECサイトの設定」のみ設定します。
「店名」「メールアドレス」「ログインID」「パスワード」を指定します。
その後、「次へ進む」をクリックします。
「データベースの設定」を行います。
「DBユーザ」、「DBパスワード」にXAMPP導入時に設定したユーザ名、パスワードを指定してください。
※「次へ進む」クリックしたら、エラーが出ました。次のようなものです。
「DB NOT FOUND」でした。原因は、「DBの種類」を「MySQL」と指定し忘れたからです。
皆様は、引っかからないようにしましょう。
次に、
「データベースの初期化」画面に進みますが、何もせず「次へ進む」をクリックします。
「データベースの初期化」結果画面が出ます。
ここでは「○○○成功しました」というメッセージを確認して「次へ進む」をクリックします。
「サイト情報について」という画面が出ます。さっと流し目くれて「次へ進む」をクリック。
インストール完了画面が出ます。「管理画面へログインする」をクリックしてください。
EC-CUBEの管理画面へ入るログイン画面が出ますので、必要事項を入力してください。
ちなみに、このアドレスがブラウザに表示されていますので、このアドレスを「お気に入り」
に入れとく楽チンです。具体的には「http://localhost/eccube/html/admin/」。
あと、表示のとおり、「index.php」を消せといわれていますので、気が向いたときに消してお
いてください。ただ、この表示は誤っていて、「index.php」の所在は、「/eccube/html/install/index.php」
にあります。
管理画面に入ると、上のような画面が表示されます。適宜設定していくこととなると思いますが、
ここでは、「ふーん、こんなんなんだ」程度でおkです。
なお、当画面の右上に「SITE CHECK」ボタンを押すと(今の時点では)初期のEC-CUBEサイトが
表示されます。
初期のEC-CUBEサイトです。
長々書いてきましたが、以上の作業でローカルXAMPP環境にEC-CUBEを導入することができました。
なお、
EC-CUBEとWordPressとの連携をしたくなったりする欲求があると思います。
この点については、
1、EC-CUBEをベースにWordPressと連携をとる
2、WordPressをベースにEC-CUBEと連携をとる
のふたつを考えると思います。
1については、無料のプラグインがありますので、実現可能性は高いと思います。
2は、WordPressの固定ページからEC-CUBEに飛ばすことを想定して実現可能性を
模索しますが、ものが「SSL」環境下で使用することが必須と考えられることから、
「セッション管理が切れる」のではないかという懸念があります。
今のところ、アドレスを分けて単体運用が、余計なトラブル抱えずに済むかなと
考えています。